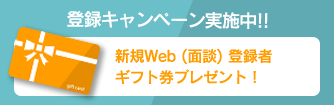Tips/コラム
USEFUL INFO
プロ通訳者・翻訳者コラム
気になる外資系企業の動向、通訳・翻訳業界の最新情報、これからの派遣のお仕事など、各業界のトレンドや旬の話題をお伝えします。

津村建一郎先生のコラム 『Every cloud has a silver lining』 東京理科大学工学部修士課程修了(経営工学修士)後、およそ30年にわたり外資系製薬メーカーにて新薬の臨床開発業務(統計解析を含む)に携わる。2009年にフリーランスとして独立し、医薬翻訳業務や、Medical writing(治験関連、承認申請関連、医学論文、WEB記事等)、翻訳スクール講師、医薬品開発に関するコンサルタント等の実務経験を多数有する。
第21回:should could wouldの訳し方
今回は「should could wouldの訳し方」について考えてみたいと思います。
まずは、文末の英文「Clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations」をザッと眺めてください。
メディカル翻訳では、人の健康・医療に係わる文書の翻訳が中心になりますが、薬物や医療は人の健康に直接的に影響を及すため、洋の東西を問わず様々な規制(regulations)に関する文書が多数あります。この規制の中には、治療ガイドラインや診断ガイドラインなど、様々な指標ガイドも含まれます。
規制やガイドラインですから、関係する当事者はそれらの内容を遵守したり、遵守するよう努力したりすることが求められます。また、その様な規制(regulations)文書には多くの助動詞(should could wouldなど)が使われています。
**********************************
文末の英文で、should could wouldなどの助動詞を検索して、その出現回数を調べてみましょう。
should:17件
could:1件
would:0件
can:1件
must:0件
will:2件
圧倒的にshouldの出現件数が多いことが解ります。
**********************************
この様に、ガイドラインなどの規制文書では助動詞、特にshouldが多数出現します。今回は、shouldを中心にこれらの助動詞の訳し方を考えてみましょう。
1.助動詞(auxiliary [helping] verb)とは
助動詞とは、文字どおり「本動詞を補助する補足的品詞・・・」と理解されている方、その理解は間違い!!!です。
助動詞は本動詞を補助しているのではなく、その動詞に対する【話者(筆者)の『意志』や『判断』を表す】本当の動詞なのです
どう言うことかと言いますと、英語では語句の並び順で文の意味を表現していますが、平叙文で主語の次に来るのは「動詞」と決まっています。しかし、助動詞は本動詞の前、つまり、主語の直後に位置していますから、本来の「動詞(主語の次に来る)」の位置を占めていることになります。ですので、助動詞が使われると言うことは、その文が話者(筆者)の『意志』や『判断』を表している文になっているということで、助動詞の無い通常の文から意味が変化しているのです(つまり、別の文になっている)。
例えば・・・
He left for Tokyo yesterday. [彼は昨日東京へ出発した。]
と言う英文は、事実を述べている文で、He(彼)に発生した事象を説明しています。ここで、話者(筆者)の意志は全く関係していません。
ところが、これに助動詞が加わると、
He may have left for Tokyo yesterday.
[彼は昨日東京へ出発したはずだ。]
となり、依然として、現在の話者(筆者)の判断を表現している文章になっています。
では、これは・・・
He can speak Japanese.
[彼は日本語を話せる。]
いくらなんでも、これはHe(彼)のことでしょ・・・と思っているあなた! 大間違いです。この文は、話者(筆者)がこれまでにHeが日本語を話しているのを聴いているなどの経験があったうえで、「彼は日本語を話せるはずだ!」と現在の話者(筆者)の判断を表現している文章になっているのです。
Heが実際に面前で日本語をしゃべっている状況を述べるのであれば、canは必要なく、He speaks (spoke) Japanese. とすれば良いのです。
2.助動詞は基本的に推量・可能性の意味
以上の様に、助動詞は話者(筆者)の『意志』や『判断』を表している訳ですが、そのニュアンスは、本動詞が「起こるかもしれな」とか「起こるかどうか解らない」とか「起こって欲しい(欲しくない)」とかの状態を表現しているのです。
例えば、 He goes to Tokyo. という平叙文を考えてみましょう。
現在の事実:He goes to Tokyo.
[彼は東京に行っている。]
現在の推量:He must go to Tokyo.
[彼は東京に行っているはずだ。]
過去の事実:He went to Tokyo, yesterday.
[彼は昨日東京に行った。]
過去の推量:He would go to Tokyo, yesterday.
[彼は昨日東京に行ったにちがいない。]
という具合に、実際はどうだか解りませんが、助動詞を使うことで話者(筆者)がある状況を推量したり、可能性を表現したりすることになります。
同様に、未来に起こることは誰にも解りませんので、未来形は全て助動詞(willやshall)を使った推量の形になります。
未来の事実:He ??? to Tokyo, tomorrow.
彼は明日東京に???。]
未来の推量:He will go to Tokyo, tomorrow.
[彼は明日東京に行くはずだ/行きます。]
3.助動詞がたくさんある理由
助動詞は
1.could
2.might
3.may
4.can
5.should
6.ought to
7.would
8.will
9.must
などが使われ、なんと9種類もあります。
話者(筆者)の『意志』や『判断』を表すのならばひとつあるいはふたつあれば十分のような気がしますが、なぜ9種類もあるのでしょうか?
その理由は、話者(筆者)の『意志』の強さや話者(筆者)の『判断』の正確性の程度を表現するためです。
程度が100%ならば、助動詞は必要なく、本動詞が確実に起こっていることを示します。一応1番のcouldの程度が一番弱く、順を追って強くなり、9番のmustが一番強いのですが、9番のmustであっても100%ではありません。ですので、推量・可能性・・・となるのです。
例えば、程度の目安は次の様な感じです。
100%: He is guilty. 彼は有罪だ。 ⇒ 裁判で有罪の判決が下った。自分で罪を認めた。
~95%: He must be guilty. 彼は有罪で間違いない。 ⇒ 判決は出ていないが、証拠が十分揃っていて、アリバイもない。
~90%: He would be guilty. 彼は有罪に違いない。 ⇒ 判決は出ていないが、証拠が十分揃っている。ただ弁護人の主張も一理はある。
~70%: He should be guilty. 彼はきっと有罪でしょう。 ⇒ 判決はまだ出ておらず、証拠はそこそこ揃っているが、弁護人の主張に同意する人もいる。
≒50%: He may be guilty. 彼は有罪でしょう。 ⇒ 判決はまだ出ておらず、証拠がそこそこ揃っていて、アリバイもあいまい。
<50%: He might be guilty. 彼は有罪かもしれない。 ⇒ 判決はまだ出ておらず、状況証拠しかなく、動機が不明。
<30%: He could be guilty. 彼はもしかすると有罪かもしれない。 ⇒ 判決はまだ出ておらず、状況証拠しかなく、動機が薄い。
ここの%はあくまで目安ですから、文章の内容や状況によって変動します。
以上の様に、様々な程度の『意志』や『判断』を表現するために、9種類の助動詞を使い分けることになります。
4.Shouldの訳し方
会話や文章でNativeが最も頻繁に使う助動詞のひとつがshouldです。
学校の授業や大学受験の参考書などでは should=・・・すべき と説明されていますので、初級のメディカル翻訳者さん達は「should」を見ると無条件に「~すべき(である)」と訳してしまいます。しかし、メディカル翻訳では「should」を「~すべき(である)」と訳すことは極めて稀です。
では、どの様に訳せば良いのでしょうか?
文末の英文「Clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations」の原文は68ページもあるガイドラインです。この原文にはなんと約160個の「should」が出てきます。ですので、1ページあたり2~3回は「should」が使われていることになります。
これほど頻繁に「should」が使われているのですから、もしこれを「~すべき(である)」としているならば、日本語版のガイドラインにも相当数の「~すべき(である)」が出てくるはずです。
そこで、同様の日本語のガイドラインを検索すると、「感染症予防ワクチンの臨床試験ガイドライン(薬食審査発0527第5号;平成22年5月27日)」という15ページ(本文14ページ)のガイドラインがみつかりました。
早速このガイドラインで「~すべきである」や「~するべき」を検索して、その出現回数を調べたところ・・・
すべきである:15回
すべき:4回
う~~~む。それなりに使われている様ですが、15回の「すべきである」で見ても1ページに1回程度しか出ていない様です。
そこで、英文でshouldが使われている文章と同様の内容の文章を調べてみたところ・・・
すること:34回
という語句が見つかりました。
14ページの本文でみますと、1ページあたり2~3回は「すること」が使われていることになり、奇しくも「Clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations」の原文と同様の使用頻度であることが解りました。
別の例としまして、医薬品の取扱い説明書である「添付文書(Package insert)」について調べてみました。
抗生物質であるアジスロマイシン(商品名:ジスロマック)の米国での添付文書(全33ページ)で、shouldの出現回数を調べたところ42回(1ページあたり約1.3回)でした。
一方、日本でのジスロマックの添付文書(全6ページ)で、「~すべきである」や「~するべき」を検索して、その出現回数を調べたところ・・・
すべきである:0回
すべき:0回
な、な、なんと1回も出てこなかったのです。
ところが「すること」の出現回数をしらべたところ・・・
すること:40回
となり、1ページあたり6~7回も出てきていたのです。
と言うことで、メディカル文章におけるshouldは「~すること」と訳すのが適切であることが解りました。その一方で、学校などで教えられてきた should=すべきである は、少なくともメディカル文章ではあまり使われないことも解りました。
以前から申しあげている様に、メディカル翻訳では通常、英和辞典の最初に出てくる訳語は「殆ど使えない」というルールが、shouldにもあてはまるのです。
完
*****************************
検討した英文:
Clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations
This document provides guidance to national regulatory authorities (NRAs), manufacturers, clinical researchers and investigators on the clinical evaluation of vaccines by outlining the data that should be obtained during the different stages of vaccine development to support an application for marketing approval. This document has been prepared in response to requests from NRAs for assistance in the evaluation of clinical trials, both during the clinical development of a new vaccine and during the regulatory review of dossiers submitted in support of applications for marketing authorization.
Vaccines are a heterogeneous class of prophylactic medicinal products containing antigenic substances capable of inducing specific, active and protective host immunity against an infective agent or toxin, or against other important antigenic substances produced by infective agents. Vaccines for human use contain one of the following: microorganisms inactivated by chemical and/or physical means that retain adequate immunogenic properties; living microorganisms that are avirulent to humans or have been selected for their attenuation whilst retaining immunogenic properties; or antigens extracted from organisms, secreted by them, or produced by recombinant DNA technology. The antigens may be in their native state, detoxified by chemical or physical means and/or aggregated, polymerized or conjugated to a carrier to increase immunogenicity.
This document also covers novel products such as DNA vaccines and live genetically engineered microorganisms used themselves as vaccines or used as carriers for other antigens. However, therapeutic vaccines (e.g. viral-vector-based gene therapy, tumour vaccines and anti-idiotypic vaccines such as monoclonal antibodies used as immunogens) are not considered here.
……
Preclinical and laboratory evaluation of vaccines
1. Production, characterization and quality assurance of candidate vaccines
The characterization, standardization and control of the components, safety and potency of vaccine preparations are key issues during development. The amount of data collected to support clinical studies should increase throughout phases I and II, and product characterization should be completed by the beginning of the phase III stage of development. In-process testing should be performed to ensure adequate control over the manufacturing process and manufacturing consistency. Analytical criteria should be established during product development and used subsequently to evaluate new batches and to establish batch-to-batch consistency. The tests adopted for routine batch release should be a selection of those tests used for the initial characterization of the vaccine. A batch release protocol providing an outline of production and a summary of the test results and establishment specifications should be available for each batch.
2. Toxicity and safety testing
Toxicity studies in animals may be considered for the assessment of the potential toxic effects of a vaccine in target organs, including the haematopoietic and immune systems as well as to assess systemic toxicity. Such studies may help to identify potential toxicity problems requiring further clinical monitoring. However, it should be recognized that a suitable animal model may not be available for undertaking toxicological evaluation of candidate vaccines, and such models are not necessarily predictive of human responses the interpretation of the results may be difficult. Furthermore, a classical repeated dose toxicity test as applied to medicines may or may not be applicable for vaccines. Applicability of repeated dose toxicity tests depends on the vaccine dose regimen and the composition of the vaccine. Usually there is no chronic exposure of the subject to a vaccine through repeated administration.
3. Potency and immunogenicity
Where relevant, potency tests should be established during vaccine development and used for routine batch release. Examples of potency assays are challenge models such as the intracerebral mouse test for pertussis and rabies vaccines, and evaluations of infectious units of live attenuated organisms for viral vaccines and bacille calmette-Guèrin (BCG). Ideally, the potency assay should mimic the clinically expected function of the vaccine in humans (as for rabies vaccine). However, in many cases, this is not possible and the assay is based on artificial challenge procedures that assess clinical protection (e.g. potency test for whole cell pertussis vaccine).
Data obtained from the immunization of animals with candidate vaccine preparations will provide valuable information to support a clinical indication. Such studies may include testing in non-human primates, but only if an appropriate disease model is available. Immunogenicity data derived from animal models can help in the selection of the doses, schedules and routes of administration to be evaluated in clinical trials. Preclinical studies should be designed to assess the relevant immune responses, e.g. seroconversion rates, geometric mean antibody titers, or cell-mediated immunity in vaccinated animals. Such studies may also address interference between antigens and/or live viruses. If a vaccine consists of more than one antigen (e.g. acellular pertussis vaccine) the response to each antigen should be evaluated. Immunogenicity studies may include the characterization of antibody class, avidity, affinity, half-life, memory, and potential induction of cell-mediated immunity as well as release of soluble mediators affecting the immune system, as appropriate.
……
Clinical evaluation of vaccines
Before the start of clinical trials (particularly phase III trials), a sound understanding of the epidemiology of the pathogen or disease of interest in the intended study population is needed. This requires population-based or outbreak evaluations of individuals exposed to, at high risk of, or suffering from, the disease in question. Such studies define disease incidence, the proportion of infected persons who develop clinical disease and the risk of transmission. The understanding of the full clinical spectrum of illness and the optimization of diagnostic criteria as well as definition of the high-risk groups frequently defined by age, gender, ethnic or population group membership, social characteristics as well as geography and seasonality of exposure, is essential for accurate vaccine evaluation.
1. Immunogenicity
In phases I, II and III, immunogenicity data are recorded as an outcome, and in certain circumstances may be used to demonstrate clinical efficacy (see below).
2. Vaccine efficacy
Vaccine efficacy could be measured as an outcome of clinical protection and/or as an immunological surrogate end-point based on immunological response. The definition of clinical cases should be given in the protocol. The inclusion of cases for whom confirmation (e.g. microbiological) was not possible should be justified in the protocol. When relevant, both clinical and serological end-points should be studied and the data presented in the report. The formula by which vaccine efficacy is calculated should be defined and validated.
The effects of vaccination at the population level depend on the coverage and distribution of the vaccine, as well as on its efficacy in preventing disease and preventing colonization (54). In addition to the intrinsic efficacy of the vaccine, its effectiveness depends on the heterogeneity in susceptibility, rates of exposure to infectious agents and protection conferred by the vaccination (55). Vaccine effectiveness may also be influenced by time-related changes in protection caused by intrinsic properties of the vaccine (waning of efficacy and boosting) (54, 56, 57), changes in vaccination coverage, and population characteristics (such as age distribution).
3. Vaccine safety
Most vaccine trials are not aimed at testing specific hypotheses regarding adverse events. Consequently, safety assessment is generally characterized by exploratory data analysis. Descriptive statistics are presented and confidence intervals are often informative. P-values may be useful for detecting signals of possible vaccine-associated adverse events for further evaluation.
If the detection of a few serious adverse events that have been specified prospectively is the primary focus of a large pre-licensure safety trial, it is advisable to consider a multiplicity adjustment for testing the corresponding small number of hypotheses. This multiplicity adjustment should be accounted for in the determination of the sample size. Otherwise, if there are no a priori hypotheses regarding specific adverse events, meaning that an undetermined number of safety analyses will be performed, adjustment for multiplicity is not generally performed during initial evaluations of the clinical trial data.
*****************************
仕事を探す
最新のお仕事情報