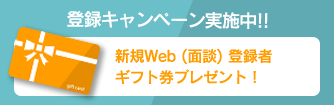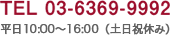Tips/コラム
USEFUL INFO
プロの視点 ー 通訳者・翻訳者コラム

『LEARN & PERFORM!』 翻訳道(みち)へようこそ 村瀬隆宗
第2回
Translate:翻訳者は翻訳するべからず?
前回は「翻訳の三原則」をご紹介しました。その第一がこれです。
Translators don't translate.
翻訳者は翻訳するべからず??まるで一休さんのトンチのようです。と、たとえても、平成生まれの方には通じないでしょうか。実は、この訳は適切ではありません。
ところで、翻訳者になるのは難しいことではありません。特に資格が必要なわけではないので、名乗って仕事を引き受けてしまえば、立派かどうかはともかく今日から翻訳者です。最近は仕事を受ける方法もクラウドソーシングをはじめ多様化しています。
では、ちゃんとした、いわゆるプロの翻訳者をその中から見分けるには、どうすればいいでしょうか。もちろん実際に翻訳してもらって仕事を評価するしかないのですが、大ざっぱに確認する方法はあります。
TOEICなどの語学資格について尋ねることも、最低限の語学力の有無をある程度は確かめられるという意味で、そのひとつです。ですが、もっと高い精度で見分けるには、こう聞いてみるといいでしょう。「英英辞典を使っていますか?」(英語関係の場合)
使っていない、ということは、英日翻訳をする際に英和辞典だけに頼っていると考えられます。ということは、主として「訳語を探す」ために辞書を使っているのではないでしょうか。しかし、翻訳は単なる言葉の置き換えではありません。
翻訳とは「原文に込められた情景や考えや主張を、別の言語で表現するプロセス」、言い換えれば「言語の壁を超えてイメージを伝える作業」だと考えられます。よく「差し引きしてはいけない」と言われますが、それは文字レベルの話ではなく、このイメージレベルの話であるはずです。
イメージを伝えるには、まずそれを自分で微に入り細に入り、正確に再現しなければなりません。この作業のためには、原文の各単語のニュアンスをしっかりくみ取る必要があります。それには、たとえば英日翻訳なら、大まかな語義を日本語で、場合によっては無理やり表した英和辞典だけでは足りず、英英辞典の活用が必須になるはずです。
そうやってイメージを再現した上で、それが読み手に伝わるように描写するわけです。ですから訳語は「探すのではなく創るもの」というのが、私の翻訳講座では合言葉になっています。
では、その英英辞典で原則1にあるtranslateを引いてみましょう。
Longman Dictionary of Contemporary English
translate: to change written or spoken words into another language
(書き言葉や話し言葉を別の言語に変えること)
おやおや、ロングマンのいうところのtranslateとは、単なる言葉の置き換えのようです。don’t translateとは、「翻訳するべからず」ということではなく、「ロングマン式translateをしてはいけない」ということでした。
ただし、オックスフォードの定義は違います。
Oxford Dictionary of English
translate: express the sense of (words or text) in another language
(言葉や文章の意味を別の言語で表現する)
こちらは「言語の壁を超えてイメージを伝える」という上の定義に近いといえそうです。たしかにロングマンのほうは言葉の定義に使える語の数が二千強と少なく、語義を表現する上で制約が大きいものの、この定義の隔たりは、それだけで説明できそうにありません。
考えてみると、イメージを伝えるためには、原著者が原文を書いた際に頭の中にあったもの、そして読み手が訳文を読んだ際に頭の中に浮かぶもの、の両方への意識が欠かせません。
一方で、機械翻訳はいくら進化しても、そこを意識することはないでしょう。機械には言葉の置き換え、ロングマンのいうtranslateをすることはできても、「翻訳」をすることは永久にできないわけです。
ですから、翻訳業界にとってのAIや機械翻訳の脅威が喧伝されるなかでも、私は落ち着いてごぶ茶をすすっております。機械によって浸食されるのは文字の置き換えであり、本当の翻訳が侵されることはない。それを信念に仕事をし、翻訳学校の授業でもそこを重視しています。

村瀬隆宗 慶応義塾大学商学部卒業。フリーランス翻訳者、アイ・エス・エス・インスティテュート 英語翻訳コース講師。 経済・金融とスポーツを中心に活躍中。金融・経済では、各業界の証券銘柄レポート、投資情報サイト、金融雑誌やマーケティング資料、 IRなどの翻訳に長年携わっている。スポーツは特にサッカーが得意分野。さらに、映画・ドラマ、ドキュメンタリーなどの映像コンテンツ、 出版へと翻訳分野の垣根を超えてマルチに対応力を発揮。また、通訳ガイドも守備範囲。家族4人と1匹のワンちゃんを支える大黒柱としてのプロ翻訳者生活は既に20年以上。
第28回:Hallucination:生成AIとの付き合い方
第25回:Share:provideやgiveより使われがちな理由
第24回:Vocabulary:翻訳者は通訳者ほど語彙力を求められない?
第21回:Excuseflation:値上げの理由は単なる口実か
第20回:ChatGPTその2:翻訳者の生成AI活用法(翻訳以外)
第19回:ChatGPTその1:AIに「真の翻訳」ができない理由
第18回:Serendipity:英語を書き続けるために偶然の出会いを
第17回:SatisfactionとGratification:翻訳業の「タイパ」を考える
第16回:No one knows me:翻訳と通訳ガイド、二刀流の苦悩
第15回:Middle out:トップダウンでもボトムアップでもなく
第14回:Resolution:まだまだ夢見る50代のライティング上達への道
第13回:Bird’s eye view:翻訳者はピクシーを目指すべき
第11回:Freelance と “Freeter”:違いを改めて考えてみる
第10回:BetrayとBelie:エリザベス女王の裏切り?
第9回:Super solo culture:おひとりさま文化と翻訳者のme time
第7回:Mis/Dis/Mal-information:情報を知識にするために
仕事を探す
最新のお仕事情報