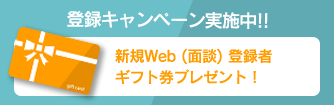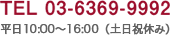Tips/コラム
USEFUL INFO
プロの視点 ー 通訳者・翻訳者コラム

『LEARN & PERFORM!』 翻訳道(みち)へようこそ 村瀬隆宗
第22回
Invoice:なぜ「インボイス制度」というのか
私のような弱小フリーランスにとってはあまりありがたくないインボイス制度が、10月から始まりました。導入の是非をめぐっては、政府で十分な議論が尽くされたようには感じませんでしたが、その半面、税と事務処理のダブル負担増を強いられる当事者を中心に、さまざまな意見が交わされました。本稿執筆時点ではまだ導入前で、反対論が根強く残っています。
私自身、いちフリーランスとして「なぜ?」という思いはあります。50代に入り、同年代の仲間とも健康や老後について語り合うようになりました。特に会社員の友人からは、定年退職後の生き甲斐や家計に関する不安を耳にします。
一方で、私にそういう不安はまったくありません。これまで磨いてきた、そして今後も磨いていく翻訳スキルさえあれば生活には一生困らないと(実際どうなるかはともかく楽天的なこともあって)信じているし、スキルを磨くプロセス自体も生き甲斐になっているからです。
翻訳に限らず、技能習得を目指すのは never too late。遅すぎることはありません。そういう生き方を奨励していくべきなのに、スキルを身に着けた上で会社ではなく己のスキルに頼る生き方、すなわちフリーランスになる障壁を高めてどうするのか。そんな「なぜ?」を問わずにはいられません。
ただ、この制度に対しては、それ以上に「なぜ?」と思ったことがあります。なぜ、インボイス制度という名前なのか? 特にフリーランス翻訳者・通訳者には、当初疑問に感じた方が多いのではないでしょうか。
語源から紐解くと、invoiceはフランス語のenvoyer(送る)から生まれたようです。商取引の記録は、アルファベットが生まれる何千年も前から行われていました。まだ紙がなかった当時のメソポタミアで、粘土板に楔形文字を刻んで「誰が誰に何を何個どんな対価で売ったか」を記録していたことは有名です。
その後、紙が発明され、age of discoveryつまり大航海時代が訪れると、遠く離れた地域間での海をまたいだ交易が盛んになり、大量の取引が売り手、買い手、物品名、数量、価格決済条件などを記載した文書にまとめられるようになりました。これがenvoisと呼ばれるようになり、英語に転じてinvoiceとなったわけです。
「送る」という意味の語源を持つため、そして交易品と一緒に送付されていたためか、invoiceは「送り状」と訳されがちで、ほとんどの英和辞典でこの語義がトップに出てきます。しかし、送り状というと、宅配便に付けるような、宛先と送り主と品名を記載しただけのもの、請求書とは別物、というイメージではないでしょうか?
ところが実際には、Cambridge Dictionary で a list of things provided or work done together with their cost, for payment at a later time と定義されているように、invoiceは金額の入った請求書として機能します。訳としても、多くの場合で「請求書」または「納付書兼請求書」が適切です。
請求書というとbillもありますが、invoiceはbillの中でも正式で形式ばった請求書という位置付けになります。大まかにいえば、飲食代や宿泊費、水道光熱費などBtoC(企業から消費者)の場合はbill、BtoB(企業間)の場合はinvoiceを使います。
昔は物品に添付されていたinvoiceですが、今はサービスにも付随します。ですから、フリーランス翻訳者も顧客に対してinvoiceを発行します。日本語関連の翻訳需要は当然、日本国外にもありますから、翻訳業には海外と比較的簡単に取引できるという特長があり(現地通貨建てなら円安下で有利)、月末になると取引先から「invoiceを送ってください」と要求されたりします。
そのため、「インボイス制度」という言葉を聞いて「<請求書制度>ってどういうこと?」と、ピンとこなかったわけです。調べてみると、この制度の正式名称は「適格請求書等保存法式」で、登録者には登録番号、適用税率、消費税額等を記載した「適格請求書」を発行・送付することが求められます。この適格請求書のことを「インボイス」と呼んでいるようです。一般名詞のinvoiceとは別物、ということですね。
名前で混乱させ、内容でも混乱させているこの制度。運用はスムーズにいき、フリーランスにとっての今後の負担が小さくなることを願うばかりです。

村瀬隆宗 慶応義塾大学商学部卒業。フリーランス翻訳者、アイ・エス・エス・インスティテュート 英語翻訳コース講師。 経済・金融とスポーツを中心に活躍中。金融・経済では、各業界の証券銘柄レポート、投資情報サイト、金融雑誌やマーケティング資料、 IRなどの翻訳に長年携わっている。スポーツは特にサッカーが得意分野。さらに、映画・ドラマ、ドキュメンタリーなどの映像コンテンツ、 出版へと翻訳分野の垣根を超えてマルチに対応力を発揮。また、通訳ガイドも守備範囲。家族4人と1匹のワンちゃんを支える大黒柱としてのプロ翻訳者生活は既に20年以上。
第28回:Hallucination:生成AIとの付き合い方
第25回:Share:provideやgiveより使われがちな理由
第24回:Vocabulary:翻訳者は通訳者ほど語彙力を求められない?
第21回:Excuseflation:値上げの理由は単なる口実か
第20回:ChatGPTその2:翻訳者の生成AI活用法(翻訳以外)
第19回:ChatGPTその1:AIに「真の翻訳」ができない理由
第18回:Serendipity:英語を書き続けるために偶然の出会いを
第17回:SatisfactionとGratification:翻訳業の「タイパ」を考える
第16回:No one knows me:翻訳と通訳ガイド、二刀流の苦悩
第15回:Middle out:トップダウンでもボトムアップでもなく
第14回:Resolution:まだまだ夢見る50代のライティング上達への道
第13回:Bird’s eye view:翻訳者はピクシーを目指すべき
第11回:Freelance と “Freeter”:違いを改めて考えてみる
第10回:BetrayとBelie:エリザベス女王の裏切り?
第9回:Super solo culture:おひとりさま文化と翻訳者のme time
第7回:Mis/Dis/Mal-information:情報を知識にするために
仕事を探す
最新のお仕事情報