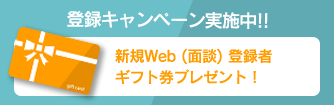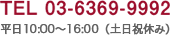Tips/コラム
USEFUL INFO
プロの視点 ー 通訳者・翻訳者コラム

『LEARN & PERFORM!』 翻訳道(みち)へようこそ 村瀬隆宗
第10回
BetrayとBelie:エリザベス女王の裏切り?
なぜでしょう。無縁とも思える遠く離れた異国の女王の死に、感傷的な気分になりました。ひとつには、王室と皇室を持つ国としてのつながりを英国に感じずにはいられないからでしょうか。それはお互いさまでもあるようで、水際対策緩和でいずれ再開できそうな通訳ガイドの仕事をしていても、英連邦からのゲストの方々には皇室への関心の高さが伺えました。
そして、第2次ベビーブーマーの自分にとって、女王は古き良き昭和を偲ばせる存在のひとりでした。その時代に幕を下ろしたのはもちろん昭和天皇の崩御ですが、女王の死去により、昭和は思い出から歴史への変化を、自分の中でまた一歩進めたように感じています。
昭和が終わったという報に接したのは友人たちと映画を観た直後で、皇室に何の関心もなかった高校生もさすがに大きな衝撃を受けました。何を観たか覚えていないほどです(『グーニーズ』だったような…)。もうひとつ印象に残ったのが、「崩御」という言葉でした。
私は上で「天皇の崩御」、「女王の死去」と使い分けましたが、今回の一連の報道を見ても、大手紙・通信社は「崩御」という表現を使っていません。翻訳用に3冊用意している用字辞典を調べてみると、時事通信社のもの(『最新用字用語ブック』)に崩御について「新聞では天皇の(死去の)場合のみ使う」とありました。
ただし、天皇ご自身は公式の哀悼の辞で「エリザベス女王陛下崩御の報に接し」とされています。ちなみに死後2時間を経てのBBCの第一報は A few moments ago Buckingham Palace announced the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II. 王室の声明はThe Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. (バルモラル城はスコットランドにある避暑用の居城、那須御用邸みたいなもの)と、特別な言葉も婉曲表現も使っていません。
その代わりに、現地やアメリカの報道を読んで個人的に印象に残ったのは、a flying carpetならぬa moving carpet(動くじゅうたん)という、愛犬家だった女王にたくさんのワンコ(主にコーギー)が付き従って歩く様子の比喩(ダイアナ妃が言い出したようです)。そして、よく目にしたbetray という単語です。
たとえばThe New York Timesの記事*1にこうありました。
She liked dogs and horses, and rarely
betray というと「裏切る」のイメージですが、女王のニュースで使われていたのは『オックスフォード新英英辞典』で定義するところのunintentionally reveal(うっかり吐露する)であり、「めったに激しい感情を見せなかった」という点が大いに強調されていました。
「めったに」の裏にある例外の代表は、1992年の出来事です。The Timesの別の記事*2にこう書かれています。
About the only public utterance that ever
王室の離婚騒動が重なり、居城が火災に遭ったこの年、女王は戴冠40周年式典で「アナス・ホリビリス」(忌まわしき年)というラテン語で心痛を表現されました。ですからAnnus Horribilisといえば1992年です。個人的には当時大学2年、女子にフラれて心の傷が癒えるまで先輩の家に寝泊まりしたことはありましたが、そんなに珍しいことではないのでホリビリスと言うほどではありません。
betrayと、ある意味反対ともいえる動詞にbelieがあります。意味としては『オックスフォード』いわくfail to give a true impression of somethingつまり「本当のイメージを与えない」。わかりやすく言えば「そんなふうには見えない」ということです。betrayが「うっかり出す」ならbelieは「出さない(隠す)」ということでしょうか。ただしbelieはほぼ常に無生物主語で使います(人を主語にしません)。
ですからbelieを使ってエリザベス女王を表現するなら
The Queen’s perfect aplomb
(悠揚迫らぬ女王の物腰は胸の内の動乱を感じさせなかった)
といったところでしょうか。ただし、belieの場合フォーカスは目的語にありますので、この文は「悠揚迫らぬ物腰とは裏腹に、女王の胸は激しくざわめいていた」という訳のほうが適しているケースが多いでしょう。
そんな君主だったからこそ、21世紀に入ってもなお多数の元植民地を旗下に置くという虚構を保つことができたのだという、女王なき英連邦の先行きを不安視する論調にも触れました。先のThe Timesの記事いわく、
「政治的発言はおろか感情の吐露さえ控えたエリザベス女王は純白のスクリーンとして、そこに投影される英連邦という幻想をつなぎとめた。変色したスクリーン、すなわち不人気で口を挟みたがる新国王に代わった今、加盟各国は過去の桎梏(しっこく)からの脱却を図る動きを強めかねない」
一方、私は皇室や王室に対して矛盾した気持ちを持っています。自分と同じように青春を楽しみ、人間らしく生きてほしい。われわれ庶民に親しめる人々でいてほしい。半面、世界に誇れる伝統を大切にしたい。そのためには、自分のような庶民とはかけ離れた、畏怖を抱かせる遠い存在であってほしい。この相反する心情を代弁する文をThe Guardianの記事*3に見つけ、改めて英国とのつながりを感じました。
We can never quite work out whether we want royals to be just like us or nothing like us.
夜中に1人で牛丼を召し上がりにいらしても何の問題もないけど、できれば世を忍ぶ仮のお姿でお願いできれば、ということでしょうか。
参考文献
*1 Kunzru, H. (2022, September 11) My Family Fought the British Empire. I Reject Its Myths. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2022/09/11/opinion/queen-hari-kunzru-imperial-delusions.html
*2 Schmemann, S. (2022, September 8) Queen Elizabeth Embodied the Myth of the Good Monarch. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2022/09/08/opinion/queen-elizabeth-dead.html
*3 Hyde, M. (2022, September 19) After the funeral, the big question: was this queen bigger than the monarchy itself? The Guardian.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/funeral-queen-monarchy-king-charles

村瀬隆宗 慶応義塾大学商学部卒業。フリーランス翻訳者、アイ・エス・エス・インスティテュート 英語翻訳コース講師。 経済・金融とスポーツを中心に活躍中。金融・経済では、各業界の証券銘柄レポート、投資情報サイト、金融雑誌やマーケティング資料、 IRなどの翻訳に長年携わっている。スポーツは特にサッカーが得意分野。さらに、映画・ドラマ、ドキュメンタリーなどの映像コンテンツ、 出版へと翻訳分野の垣根を超えてマルチに対応力を発揮。また、通訳ガイドも守備範囲。家族4人と1匹のワンちゃんを支える大黒柱としてのプロ翻訳者生活は既に20年以上。
第28回:Hallucination:生成AIとの付き合い方
第25回:Share:provideやgiveより使われがちな理由
第24回:Vocabulary:翻訳者は通訳者ほど語彙力を求められない?
第21回:Excuseflation:値上げの理由は単なる口実か
第20回:ChatGPTその2:翻訳者の生成AI活用法(翻訳以外)
第19回:ChatGPTその1:AIに「真の翻訳」ができない理由
第18回:Serendipity:英語を書き続けるために偶然の出会いを
第17回:SatisfactionとGratification:翻訳業の「タイパ」を考える
第16回:No one knows me:翻訳と通訳ガイド、二刀流の苦悩
第15回:Middle out:トップダウンでもボトムアップでもなく
第14回:Resolution:まだまだ夢見る50代のライティング上達への道
第13回:Bird’s eye view:翻訳者はピクシーを目指すべき
第11回:Freelance と “Freeter”:違いを改めて考えてみる
第10回:BetrayとBelie:エリザベス女王の裏切り?
第9回:Super solo culture:おひとりさま文化と翻訳者のme time
第7回:Mis/Dis/Mal-information:情報を知識にするために
仕事を探す
最新のお仕事情報