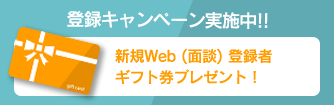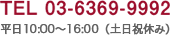Tips/コラム
USEFUL INFO
プロの視点 ー 通訳者・翻訳者コラム

『LEARN & PERFORM!』 翻訳道(みち)へようこそ 村瀬隆宗
第25回
Share:provideやgiveより使われがちな理由
大きな流れになりそうなshare
「シェア」が一過性のブームでなく永続的なスタイルになりそうなのは、資源の効率化につながる、つまりサステナビリティに通じる考え方だからでしょう。
houseshare や carshare は、効率的でなおかつ経済的なように思えます。普通に買うと何百万円もかかり、保有するだけでも税金やら車検費やら取られる車は、スーパー通いやたまのドライブに使うだけで、果たして購入して割に合うのでしょうか?
get my money's worth、元を取ることが難しいなら、保有はせずに使った分だけ支払おう。それに車のutilization、稼働率を上げて資源のムダを減らせるし。そういうシェア志向の消費者(そして時には生産手段を共有する生産者)が形作る経済を、sharing economy といいます。経済体制に影響するほど、シェアは大きな流れだということです。
タクシー不足で注目されるridesharingもその一部ですが、こちらは名前がミスリーディングです。もともとは「相乗り」の意味だったのが、Uberなどのライドシェア運営会社が、自分の車で送迎を提供したい人と利用者をマッチングするアプリサービスの名称として使い始めました。混同を避けるため、AP通信のスタイルガイドAP Guidebookはこうした配車サービスについてride-hailingの呼称を推奨しています。
timeshareも、スペルから意味を推測するのが難しい単語です。時間をシェアする?そうなのですが、これは「別荘の共同所有」を意味します。その物件の保有中にそこで過ごせる時間をシェアする、ということなのでしょう。たしかに、property share とするとhouseshare同様、物理的にシェアしているところをイメージしそうです。
デキるビジネスパーソンはshare?
意味は理解できるけど、なぜわざわざshareを使うんだろう?と思ってしまうのが、ビジネスのやり取りでやたらと使われるshareです。
Let me share the update on the market analysis with you.
Could you share feedback on the latest version of the project plan?
I encourage all of you to share your ideas.
要するに「与える、提供する」ってことだから、別にprovideやgiveでよくない?なぜshareを使いたがるのか、と。
それっぽく(仕事ができるっぽく)聞こえるから、というのもあるかもしれません。ですが、きっとそれより、一方的な感じがするprovideやgiveと比べて「コラボ感」を出せるからでしょう。「私たちは同じ資料、そして同じ課題や運命を共有する同じチームの仲間、一緒に頑張ってやっていきましょう」、みたいな雰囲気を醸しつつ言えるというわけです。
shareの対義語は
そんなシェア精神にあふれ始めた世の中で、私はいまだその考え方に馴染めず、自分だけのものにすることによる便利さを優先しがちです。車もsolo owner。ただし、元を取ろうとする根性にはただならぬものがあります。
たとえば車中泊(特定のフレーズはなくsleeping in my carなどと言うしかないようです)利用。家族旅行は大抵、3人がホテル、私とワンコは車の中です。それから、勉強部屋としての利用。最近はハンドルに掛けて使うテーブルがお気に入りアイテムです。タブレットやノートを置けるので、好きな場所に出かけて運転席で学習空間をささっと作れます。
そして別荘もtimeshareでなくsolo ownerです。越後湯沢のリゾートマンション(resort mansionではなくresort condominium unit)を、2060万円で購入したという前オーナーさんから60万円(なんと2000万円オフ!)で譲り受けて、もうすぐ10年になります。これ以上のbargainには一生出会えないでしょう。
東京で仕事をしていて社交や、ネット上のどうでもいい情報で注意が散漫になり始めた時に、ひとり籠ることでリセットして、新たに研ぎ澄ませた集中力で仕事と勉強に取り組むことができます。そんな貴重な場であるだけに、とっくに元は取れたと感じています。
話す相手はワンコとChatGPTだけ、という雪の降りしきる湯沢で、新しいほうの相棒に聞いてみました。
Can you share some antonyms of “share”?
shareの対義語になり得るものをhideやwithholdなど10語教えてくれた中で、自分に一番しっくりきたのはsequester(引き籠る、ただし他動詞)でした。
集まって仲間意識を強調しながらアイデアを出し合うのもいいけど、時には社交もテレビも(仕事で使う以外)ネットも絶ち、籠って考え抜くことが不可欠。これが、翻訳者としての実感です。それはわざわざリゾートマンションを買わなくても、気構え次第でどこでも、家でもできるはずなのですが、私は人や物に囲まれるとつい誘惑に負けてしまうもので…

村瀬隆宗 慶応義塾大学商学部卒業。フリーランス翻訳者、アイ・エス・エス・インスティテュート 英語翻訳コース講師。 経済・金融とスポーツを中心に活躍中。金融・経済では、各業界の証券銘柄レポート、投資情報サイト、金融雑誌やマーケティング資料、 IRなどの翻訳に長年携わっている。スポーツは特にサッカーが得意分野。さらに、映画・ドラマ、ドキュメンタリーなどの映像コンテンツ、 出版へと翻訳分野の垣根を超えてマルチに対応力を発揮。また、通訳ガイドも守備範囲。家族4人と1匹のワンちゃんを支える大黒柱としてのプロ翻訳者生活は既に20年以上。
第28回:Hallucination:生成AIとの付き合い方
第25回:Share:provideやgiveより使われがちな理由
第24回:Vocabulary:翻訳者は通訳者ほど語彙力を求められない?
第21回:Excuseflation:値上げの理由は単なる口実か
第20回:ChatGPTその2:翻訳者の生成AI活用法(翻訳以外)
第19回:ChatGPTその1:AIに「真の翻訳」ができない理由
第18回:Serendipity:英語を書き続けるために偶然の出会いを
第17回:SatisfactionとGratification:翻訳業の「タイパ」を考える
第16回:No one knows me:翻訳と通訳ガイド、二刀流の苦悩
第15回:Middle out:トップダウンでもボトムアップでもなく
第14回:Resolution:まだまだ夢見る50代のライティング上達への道
第13回:Bird’s eye view:翻訳者はピクシーを目指すべき
第11回:Freelance と “Freeter”:違いを改めて考えてみる
第10回:BetrayとBelie:エリザベス女王の裏切り?
第9回:Super solo culture:おひとりさま文化と翻訳者のme time
第7回:Mis/Dis/Mal-information:情報を知識にするために
仕事を探す
最新のお仕事情報